久保田一竹は、日本の染色工芸の巨匠として、約20年にわたる「辻が花」の研究と革新により、伝統技法に新たな息吹を吹き込みました。ここでは、彼の生涯、挑戦、作品世界、国際的評価、そして文化的遺産としての意義について、章立てで詳しくご紹介します。
第1章 久保田一竹のプロフィール
1917年10月7日、東京・神田(現在の中央区千代田区)に骨董屋の息子として生まれた久保田一竹は、14歳で染色の世界に足を踏み入れ、1931年に友禅師・小林清に師事しました。その後、1934年に大橋月皎の下で人物画を、1936年に北川春耕の下で日本画(山水・水墨画)を学び、幅広い芸術的感性を養います。
20歳の時、東京国立博物館(当時の帝室博物館)で室町時代の「辻が花」の小裂に出会い、強烈な衝撃と共に「いつか自らの手で復刻させたい」という夢を抱くようになりました。しかし、太平洋戦争に応召され、27歳で戦争に参加、終戦後はシベリアへの抑留という困難に見舞われ、研究が一時中断されます。
31歳で復員後、再び「辻が花」の研究に着手し、40歳以降は専念できる環境の中で徹底的に技法を磨きました。そして、60歳(1977年頃)に、独自の構成と染色法―「一竹染」と呼ばれる技法―を用いた自己流の「一竹辻が花」を確立。1983年にはパリ・チェルヌスキ美術館で個展を開催、1988年にはバチカン宮殿で創作能「イエズスの洗礼」の衣装制作を手がけるなど、国内外で高い評価を獲得しました。
さらに、1990年にフランス芸術文化勲章シュヴァリエ章、1993年に文化庁長官賞を受賞。1994年には河口湖町に久保田一竹美術館を開館し、作品集『一竹辻が花 光の響』も出版されています。化学染料を駆使した鮮やかで重厚な色合いは、彼の作品の大きな魅力となっており、富士山を望む絶好のロケーションで鑑賞できる美術館は、多くの来館者に愛されています。
第2章 「辻が花」再興への挑戦と技法の革新
久保田一竹の人生を大きく変えたのは、20歳で出会った「辻が花」の小裂でした。この出会いが彼に、かつて室町時代に流行しながらも江戸時代初期に途絶えた幻の染色技法を復興させるという強い決意を抱かせます。
しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。戦争への参加とシベリア抑留という試練を乗り越え、復員後、40歳から本格的な研究に専念。約20年の歳月をかけた試行錯誤の末、60歳頃に独自の染色法と構図を確立し、「一竹辻が花」としてその美を現代に蘇らせました。
技法革新の主なポイント
-
化学染料の積極的使用
伝統的な染色では扱いが難しい化学染料を敢えて使用。ぬるま湯で調合する独自の技法により、従来にはなかった多彩で深みのある色彩表現を実現しました。 -
独自の構図と表現
絵画的なダイナミズムを取り入れ、重ね染めや厚みのある絞り染めを組み合わせることで、伝統に新しい表情と華やかさを与えています。 -
「一竹辻が花特殊生地」の開発
一竹工房別織による特殊三重織の高級生地に特殊金通しを施し、しなやかさと光沢を実現。作品全体の質感を高める重要な要素となっています。 -
「一竹星」の導入
コバルトブルーの小さな星「一竹星」は、シベリア抑留中に見たオーロラと星の輝きを再現したもので、作品に独自のアクセントを与え、彼の挑戦の象徴として高い評価を得ています。
このように、久保田一竹は伝統技法に革新的なアイデアを融合させることで、単なる再現にとどまらない「一竹辻が花」という新たな芸術様式を確立しました。
第3章 久保田一竹の作品世界とその特徴
久保田一竹の作品世界は、失われた「辻が花」に対する情熱と、自然や自身の体験から得たインスピレーションが凝縮されたものです。彼の「一竹辻が花」は、伝統的な絞り染め技法を踏襲しつつも、独自の技法革新によって新たな美意識を表現しています。
作品の主な特徴
-
伝統と革新の融合
20年余りにわたる研究の末に確立された「一竹辻が花」は、従来の縫い取り絞り、帽子絞り、桶絞りといった技法を基盤としながらも、独自の重ね染めやダイナミックな構図によって、革新的な美しさを実現しています。 -
化学染料による鮮やかさ
独自の技法で化学染料をぬるま湯で調合し、従来の着物では難しかった深みと重厚な色彩を可能に。作品全体に鮮やかでありながらも力強い印象を与えます。 -
多様な絞り染めの技法
数百種類にも及ぶ絞り技法が用いられ、布一枚ごとに異なる模様やグラデーションが生み出されるため、作品は見るたびに新たな発見と感動を呼び起こします。 -
「一竹星」の象徴性
すべての作品に取り入れられる小さなコバルトブルーの星「一竹星」は、シベリアでの体験から得た輝きを表現し、彼の独自性と革新性を象徴するモチーフとなっています。 -
独自の生地と構成
一竹工房別織の特殊三重織生地を使用し、特殊金通しで仕上げた生地は、しなやかでありながら光沢を放ち、作品の質感と存在感を一層引き立てています。 -
ダイナミックな構図と自然へのオマージュ
四季、海、宇宙、そして富士山など、自然の壮大なテーマを大胆な構図で描き出し、見る者に深い感動を与えます。また、実用着物としての美しさも追求し、「花戯」や「瑞華」など、日常に溶け込む芸術としても評価されています。 -
連作「光響」
代表作の一つである「光響」は、春・夏・秋・冬、海、宇宙をそれぞれ80連作で表現する壮大な試み。未完部分は弟子たちにより受け継がれ、今もなおその制作が続けられています。
さらに、河口湖に佇む久保田一竹美術館は、彼の作品世界を余すところなく体現しており、建築や庭園にも彼の美意識が反映されています。
第4章 国際的評価と文化的遺産としての意義
久保田一竹が創り上げた「一竹辻が花」は、その独創性と芸術性の高さから、国内外で高い評価を受け、日本の重要な文化的遺産として位置づけられています。
国際的評価
-
海外展開の先駆け
1983年、パリのチェルヌスキ美術館で開催された「一竹辻が花展」を皮切りに、ニューヨーク、ダラス、ロンドン、ブラッセル、ロッテルダム、マドリッド、バルセロナ、サラゴサ、パリなど、ヨーロッパの主要都市で個展が開催され、国際的な注目を集めました。 -
権威ある受賞と評価
1990年にはフランス政府よりフランス芸術文化勲章シュヴァリエ章を受章。さらに、1996年にはワシントンD.C.のスミソニアン国立自然史博物館で個展を開き、米国においても高い評価を得、博物館からは感謝状が授与されました。 -
美術館の国際的人気
久保田一竹美術館は、ミシュラン観光ガイドで3つ星を獲得するなど、海外からの観光客や専門分野の学生からも絶大な支持を受け、日本の伝統文化が世界で認められている証となっています。
文化的遺産としての意義
-
伝統染色技法の復興と革新
室町時代に流行し、江戸時代初期に衰退した「辻が花」を、約20年の研究と独自の技法革新により再興。伝統を単に再現するのではなく、化学染料の使用で従来の技法にはなかった鮮やかさと重厚感を実現しました。 -
独自の美意識とデザイン要素
「一竹辻が花」は、伝統的な絞り染めの技法に加え、独自の重ね染め、ダイナミックな構図、そして「一竹星」と呼ばれる象徴的なモチーフを組み合わせることで、新たな芸術様式として確立されました。 -
継承と未来への展望
1994年に河口湖に開館した久保田一竹美術館は、彼の作品を保存・公開する重要な拠点であると同時に、「人と自然と芸術の三位一体」という彼の理念を体現する場となっています。また、2代目の久保田悟嗣氏がその技術と精神を受け継ぎ、未来へと継承している点も大きな意義を持っています。
久保田一竹の功績は、一度失われた伝統染色技法を現代に蘇らせ、独自の革新を加えることで、世界に誇る新たな芸術を創造したことにあります。その作品は、単なる染色工芸の域を超え、日本の伝統文化と美意識の象徴として、今後も末永く受け継がれていくことでしょう。
第5章 まとめ
久保田一竹は、20年以上にわたる「辻が花」への情熱と不断の探求心により、伝統染色技法に革新をもたらしました。彼が確立した「一竹辻が花」は、化学染料を活用した鮮やかな色彩、独自の絞り染め技法、そして動的な構図と自然への敬愛を融合させた、唯一無二の芸術様式です。
国内外で高い評価を受けた彼の業績は、パリ、ワシントンD.C.などの国際舞台での展示や各種賞の受賞により証明されるとともに、河口湖の美術館を通じて次世代へと受け継がれています。
このように、久保田一竹の足跡と作品世界は、伝統と革新の融合、そして人と自然と芸術の調和を体現する文化的遺産として、現代に甦る「辻が花」の美を私たちに伝え続けています。
→久保田一竹の商品を見る
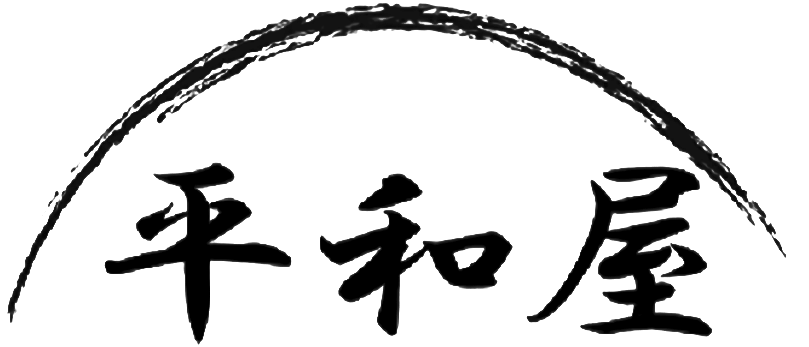



シェア:
北村武資紹介コラム―伝統技術と独自の作風が光る着物の魅力
佐々木苑子:和装の伝統と革新を紡ぐ名匠の世界